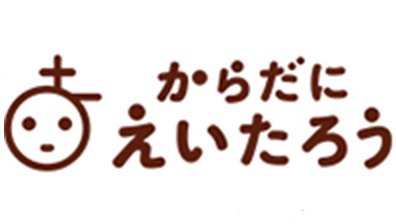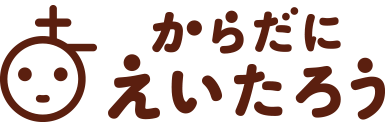今回は「樓の字事件」のお話です。
「屋号」のお話の中で触れていました「郎」の字がふさわしくないというのはどういう内容のことだったのですか?(2024年6月配信「屋号」を参照)
「井筒屋」から屋号を「榮太樓」にしたいきさつは前回のお話で述べましたが、店の屋号である以上、その字は「栄太郎」ではなく「榮太樓」と書くのも当然の成り行きではありました。
ところがある日突然、嵯峨御所・大覚寺の寺侍と自称する数人が店頭に現れ、「樓という字は『たかどの』という意味で格式の高い字であるのに、一介の菓子屋が使用するとは身の程知らずである」と因縁をつけてきたのです。
そして何かしらの挨拶があれば使用許可のお墨付けを与えても良い、とゆすり、たかりのようなことがあったそうです。
榮太樓初代はやむなくいくらかの金子を渡し許可を得て「榮太樓」の屋号を名乗ることができました。
後日、寺侍は厚手で白くちりめんのようなしわのある紙の中央に「樓」と書かれ下に大きな朱印が押してある許可証を持参してきたといいます。
どのような内容が書かれていたかは残念ながら関東大震災で焼失してしまったため残っておりません。
このことは「樓の字事件」と記録に残され、先代の記憶の中のお話として聞き伝わっております。