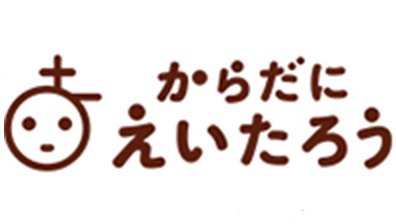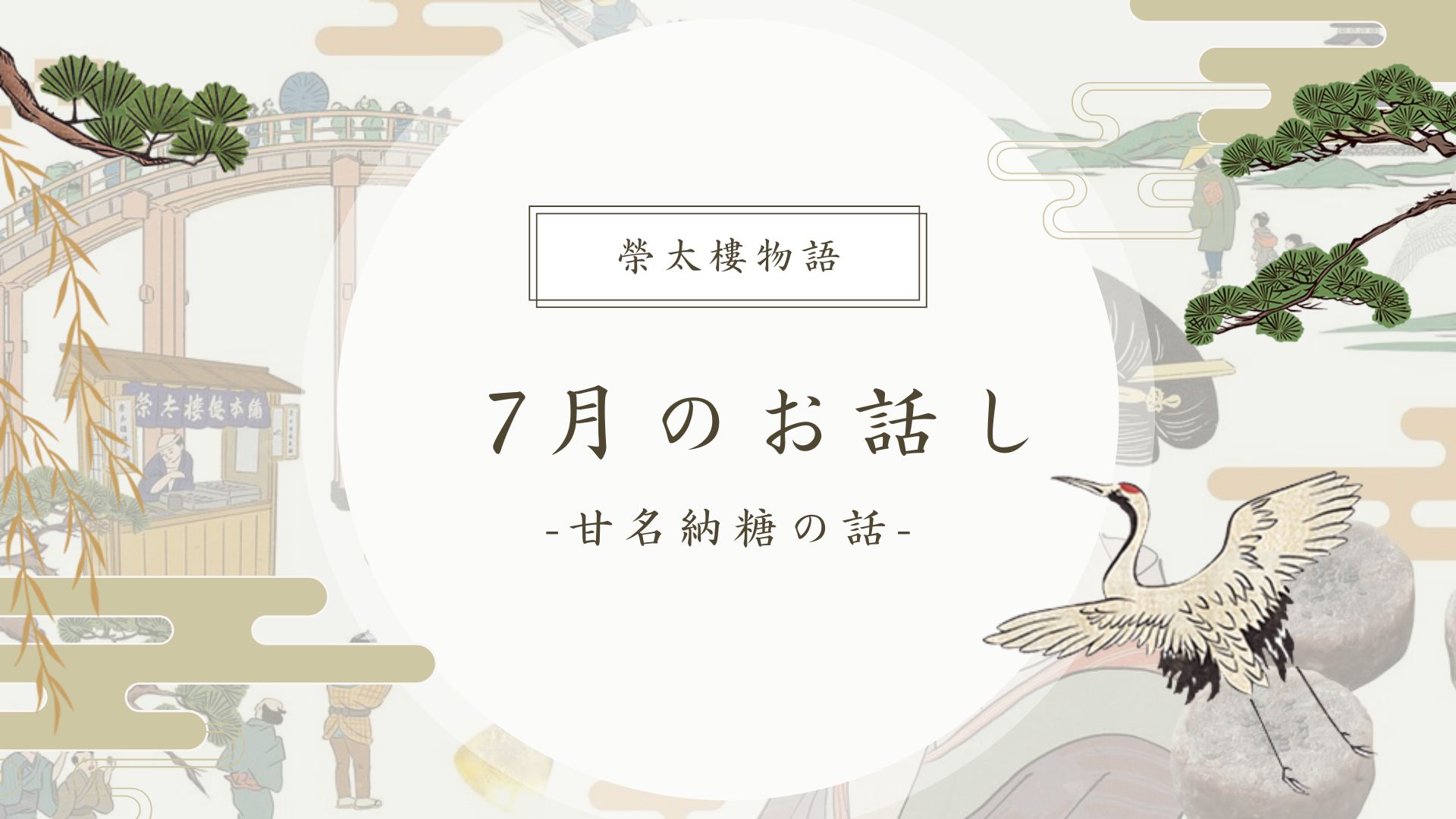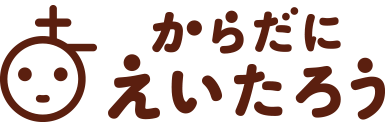江戸当時、この甘名納糖は生菓子よりも遥かに日保ちがし、塩豆やピーナッツなどのように一度食べだすと止まらなくなるスナック菓子の先駆けとも言えます。
今回は「甘名納糖(あまななっとう)」のお話です。
甘名納糖はいつ頃うまれ、なぜ「あまななっとう」と呼ばれるのですか?
甘名納糖は榮太樓初代が1861~1864年(文久年間)に創製したもので、日本橋の橋の袂で生まれたチャキチャキの江戸っ子気質が詰まった江戸菓子です。
当時まだ菓子が一般庶民にとって高嶺の花であったものを、少しでも安価に。また、生菓子のように保存がきかず、量産もできないものだけを売っていたのでは、これからのお客様のご要望に応えられない、ということで開発されました。
原料は小豆ではなく、「金時大角豆(きんときささげ)」を使います。
大角豆(ささげ)は、餡にするには不向きで使用されず御赤飯用の豆くらいにしか用途がなかったため安かったこと。また小豆は煮ると皮が割れることで「切腹」を嫌う武士に縁起が悪いと言われ、大角豆の皮は堅く、煮ても割れないことから使用しています。
製造方法も一度に大量生産でき、その風味も蜜煮(みつに)することで独特な味が完成しました。
何よりも日保ちがすることで初代の開発意図をすべて総括された画期的商品が生まれました。
この素晴らしい商品に何という菓銘をつけようか。初代は、当時交友のあった文人墨客たちにも知恵を借りました。
その中の一人がこれを食べ、「遠州浜松の名物『浜名納豆』をもじって『甘名納糖』と名付けたらどうか」と言いました。
初代も喜びその菓銘に決めたと残されています。
のちにこの甘名納糖は和菓子の新しいジャンルとして日本中で製造されるようになりました。
菓銘も「あまななっとう」では言いにくいため「甘納豆」と略されて呼ばれるようになり現在に至ります。
1877年(明治10)に開催された「第一回内国勧業博覧会」では甘名納糖が優等賞を受賞し、戦前までは看板商品の「梅ぼ志飴」を凌ぐ人気があったと記録されています。
また甘名納糖の姉妹品として明治20年代に白隠元を原料とした「村時雨(むらしぐれ)」という商品がありました。こちらも全国で初めて作ったのが榮太樓です。
なお、この村時雨は昭和天皇が皇太子時代だった1921年(大正10)3月から半年間、欧州五か国ご訪問の折、当社にご用命があり、お納めした話が残されています。
榮太樓では創製当時の姿を正しく守るために今でも原料は「金時大角豆(きんときささげ)」を使い、「甘名納糖」と称して販売しています。
現在では日本橋本店でしかお買い求めできない限定商品となっております。
ぜひご賞味くださいませ。