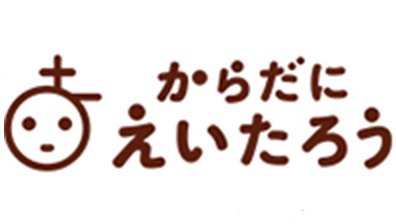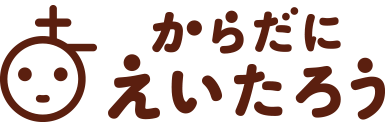激動の明治時代から昭和の終戦にかけて50年来、榮太樓を支えた榮太樓二代目のお話しです。
榮太樓初代のお話はよく聞きますが、二代目榮太樓とはどのような人物だったのですか?
二代目榮太樓の仲次郎は実父である榮太樓初代の突然の死去により22歳という若さで榮太樓の当主となりました。
明治、大正、昭和の終戦まで榮太樓の家業や菓子業界の発展に大きく貢献しました。
また貴族議員をはじめ多くの団体に公職を通じて活動していました。
明治40年代には代表菓子である「梅ぼ志飴」「甘名納糖」の容器としてブリキ印刷缶を採用し、長期保存と品質保持に大いに役立てたほか、量産販売が成功し売上増大に繋がることになります。
また当時珍しかったレジスターを店頭に導入し、金銭授受の方法をいち早く近代化させました。個人商店としては初めて導入されたレジを物珍しさも手伝って見学に訪れる人が多かったそう。
明治時代には東京繁盛菓子店の人気度を相撲番付に見立てた人気番付表「東京盛大蒸菓子店一覧表」ではたびたび大関として格付けされるなど当時の繁盛ぶりが垣間見えます。
大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災では店舗、工場が全焼するも、直ちに焼け跡の復興に着手し、50日後にはバラック建ての仮店舗を急造、仮営業を開始させました。
現店舗の場所に翌年1月に営業を開始すると日本橋区内で復興を成し遂げた店がまだ少なく、開店初日にはお客様が殺到して販売ケースが押し潰されるといったハプニングが発生したと記録に残されています。
将来を見据えて復興後は個人名義であった会社を法人化させ時代の動きを見極めていきました。
また政界においては大正6年(1917)より三期12年、日本橋区会議員を務め、区政に参画していたが、昭和7年(1932)から二期、貴族院多額納税議員に選出されました。
一菓子業の身をもって国政に参与する栄誉を担い、「榮太樓」という菓子屋の名前を世に広めていきました。