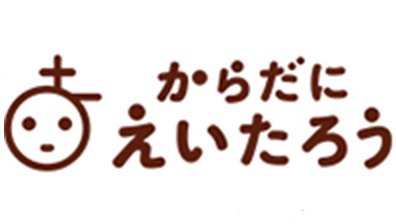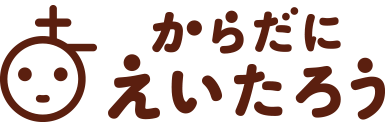榮太樓が生み出した菓子の一つといわれている「玉だれ」について教えてください。
玉だれはわさびと砂糖で作った餡を求肥で巻いた菓子で甘名納糖とともに榮太樓初代によって明治10年代に創製されました。これも甘名納糖と同様に正真正銘「江戸菓子」です。
もう一つ強調しておきたいことは、主原料の一つに「山葵(わさび)」を使用していること。わさびとは日本独特の香辛料ですが、それを菓子という甘いものに使用した製品は日本でも唯一です。従って「玉だれ」とは世界でたった一つしかないユニークな菓子ということになります。
なぜ初代はこれほど異色で大胆な発想の菓子を生み出したのでしょうか。そのきっかけや意図については細かく残されておりませんが、「日本橋には青物市場があり(現在のコレド日本橋裏あたりは当時「青物町」といった)そこで伊豆湯ヶ島のわさびを扱っておりこの商品のヒントになった」という。わさびの独特な香りを生かし、その芯を巻いている白い求肥越しに透けて見えるわさびの緑が、涼感を呼び起こします。こうした色彩感覚に訴える初代の着想には、深い感銘を覚えます。
玉だれの菓銘由来は謡曲・能の中でも名曲にして難曲である「小町物」の一つである「鸚鵡小町(おうむこまち)」の一節から取られたもので、年老いた小野小町を労って時の帝である陽成天皇が「雲の上はありし昔に変らねど見し玉簾(たまだれ)の内やゆかしき」と問いかけの和歌を詠んだところ、小町は鸚鵡返しとして即座に「雲の上はありし昔に変らねど見し玉簾(たまだれ)の内ぞゆかしき」と「や」と「ぞ」を一文字変えて返歌を詠んだという。
玉簾の内(玉簾とはすだれの美称でありこの場合は御殿の御簾の内側、即ち宮中での生活を指す)という内容で、「宮中での生活はとても懐かしく思います」というのが返歌の意味です。この歌詞にある「玉だれ」という言葉からこの菓子の持つ香り、色彩感覚、姿、形、そしてその中に秘められた味などを想い、菓銘としました。